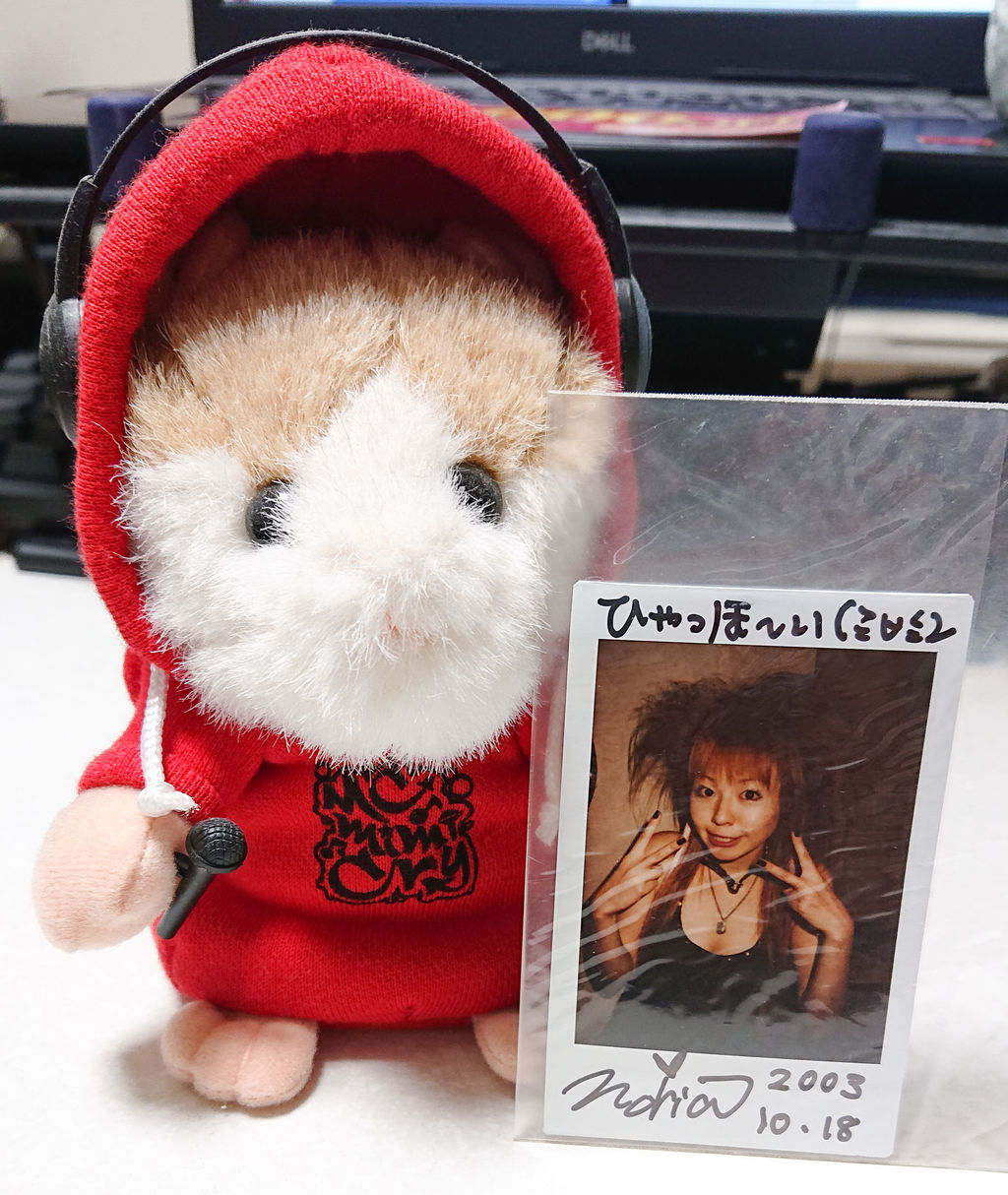前の記事>DDRの思い出 16 ― EXTREME編 5
最初の記事>DDRの思い出 1 ― 出会い編
最初の記事>DDRの思い出 1 ― 出会い編
2006年春、無事に大学に合格した僕は上京した。DDR SuperNOVAの稼動開始予定は7月だったのでもう目と鼻の先なのだが、SuperNOVAが稼動するまでの数ヶ月の間DDRを全くやらないわけはなかった。渋谷から2駅のところに引っ越したため、渋谷でDDR EXTREMEが稼動しているゲーセンを探したところ、幸いにも存在していたため、そこが僕の新しいホームとなった。今は無き渋谷会館である。
一番たくさん足を運んだのは渋谷会館だったが、他にEXTREMEのあったゲーセンだと、池袋BSGにも少しだけ行ったことを覚えている。このゲーセンはSuperNOVA以降も何かと縁がある思い出の場所である。EXTREMEの時は確かBSGのDDRは2台置いてあっただろうか(違ってたら申し訳ない)。また、DDR以外の音ゲーの設置台数がどれもこれも多く、東京の凄さに改めて驚愕した覚えがある。
SuperNOVA稼動までたった数ヶ月ではあったが、その期間にもDDRつながりでちらほら知り合いができた。渋谷会館にもコミュニケーションノートが置いてあったため、そこから始まる交流もあった。DDRで僕と知り合った人はほとんどSuperNOVA以降だと思うので、EXTREMEの頃の僕を知っている人は結構レアである。
ちなみに当時の僕は、親しくなっても相手の本名を知らないままハンドルネームで呼び合うというオタクの文化を本当に知らなかったので、何人かには相手の本名を素で尋ねた覚えがある(SuperNOVA稼動後もしばらくやってたと思う)。そのたびに怪訝な顔をされるのだが、大体みんな教えてくれた気がする。もし当時それで不愉快な思いをされた方がいたら申し訳ない。
大学入学後わりとすぐに授業をサボりがちになり渋谷会館に通う日々を送っていたが、あるとき渋谷会館にてDDRがめちゃくちゃ上手いプレイヤーを見かけた。それが僕とJun-Gさん(通称タンクさん)との出会いだった。タンクさんと親しくなったのはSuperNOVA稼動後だったと思うが、以後タンクさんにはたくさん構っていただき、タンクさん経由でDDRの知り合いもたくさん増え、それに比例するようにDDRのモチベーションも高くなっていったので、タンクさんとの出会いがなければ今の僕はないと言っても過言ではないのである。
渋谷会館で初めて見たタンクさんのプレイはとにかく上手かったので、やっぱ東京は違うなと思ったことを覚えている。タンクさんと僕以外にDDRをプレイする客はほとんどおらず、基本的に2人で交互にプレイしていた。その時タンクさんのプレイを見て気づいたのだが、タンクさんは特定のいくつかの曲を練習しているようだった。実は、近い内に都内近郊のゲーセンでDDRの大会が開催される予定があり、僕もたまたまネットで見かけてそのことを知っていた。タンクさんがプレイしていた曲の大半がその大会の課題曲だったため、僕は「この人はその大会に出る予定があり、その練習をしているんだろうな」と察したのだった。
それを知った途端、僕よりも上手い人が大会のために練習している貴重な時間を、僕がプレイすることで半分奪ってしまっていることが非常に申し訳なくなってきた。耐え兼ねた僕は、帰り際に「すみません、大会の練習の邪魔になりませんでしたか……?」と、タンクさんに声をかけてしまった。そんなこと言われたって言われたほうも反応に困ると思うのだが、その時の僕はそれを言わずにいられなかったのだった。その時のタンクさんの返事は「いえ、順番なんで……」という、まあそりゃそうなるよなという感じのものだった。これがタンクさんと僕の初めての会話である。
このことは後にタンクさんからもネタにされて、「昔のお前はあんなに腰が低かったのにな〜」といじられたりしたのであるが、僕はいつだってタンクさんへの感謝と尊敬の念を忘れたことはないのだ。
そして2006年7月、ついに待ちに待ったDDR SuperNOVAが稼動を開始した。ここから先は本当にたくさんの思い出があるのだが、元々このDDR思い出語りは、東京でDDRの知り合いがたくさんできる前の話をするために始めたものなので、ひとまずこの記事を最後に更新は終わろうと思う。SuperNOVA以降の話も読みたいという人もいるかもしれないが、ご容赦いただきたい。
そもそもSuperNOVA以降の話なんて書き始めたら、これまでとは比べ物にならないくらい凄まじい分量になってしまう。2ndからEXTREMEまで約7年間の思い出を17回に渡って書いてきたが、プレイ回数だけ見ても、その7年間におけるアーケードDDRのトータルプレイ回数を、1年間のSuperNOVAだけで悠々と超えてしまっていると思う。ちなみにSuperNOVA及びSuperNOVA2のプレイ回数は、どちらも3400回ほどであった。
とはいえ、SuperNOVA以降の話を書くつもりが一切ないかというとそういうわけでもない。いつになるかはわからないが、そのうち気が向いたらまた続きを書くかもしれない。
最後に、このブログの古い記事はほとんど削除してしまっているのだが、SuperNOVA稼動日の日記とSuperNOVAでONE MORE EXTRA STAGEを初めてクリアした時の日記のデータが残っていたので、特別に再公開することにする。
以上、ここまでお付き合いいただきありがとうございました∩・ω・)∩
終わり。